投稿日:2025年5月7日
遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことを「遺言執行者」といいます。
シンプルに、遺言による手続きを進める人と言った方が分かり易いかもしれません。
今回はこの遺言執行者について解説します。
遺言により財産を取得させる場合、「相続させる」と書く方法と、「遺贈する」と書く方法があります(この住み分け、違いは長くなるので今回は割愛します。)が、「遺贈する」と書いた場合、原則として遺言執行者がその手続きを行います。
原則としてと書いたのは、財産をもらう人(受遺者)が相続人の場合、「遺贈する」と書いてあっても、受遺者が単独で不動産の相続登記(所有権移転登記)を行うことができるからです。
とは言え、一部例外を除けば、「遺贈する」と書いてあれば遺言執行者が必要と思っても大きな間違いではありません。
遺言執行者は弁護士じゃない人を指定することもできますし、財産をもらう人を指定することもできます。例えば、「長男に自宅を遺贈する。本件遺贈の執行者として長男を指定する。」と書いても問題ありません。
また、複数の人を遺言執行者として指定することもできますし、法人を指定することもできます。
指定できないのは未成年者や破産者等一定の人に限られます。
遺言で指定された遺言執行者は、就任を承諾するのか、辞退するのか自由に決めることができます。指定された遺言執行者が就任を辞退した場合、利害関係者は家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てを行わなければいけません。
注意が必要なのは「認知」と「廃除」です。
「認知」とは法律上の婚姻関係によらず生まれた子を自分の子だと認める行為であり、「廃除」とは相続人の地位を剥奪することです。
この2つは、遺言執行者による執行が必須な行為ですので気を付けて下さい。
その他、注意点を列挙します。
①遺言執行者が作成する相続財産目録は、執行の対象となっている財産についてだけ記載すれば足りる。
②遺留分を侵害している内容の遺言であっても、遺言執行者はそのまま執行して構わない。
③生命保険の受取人変更も遺言執行者が行うことができるが、遺言者が死亡した際、その旨を保険会社に通知する必要がある。
遺言執行者を指定すると、執行時に報酬がかかったり、全相続人に相続財産目録を開示する義務が生じたりと、後々問題となる場合がありますので、安易に考えず、どうしたら良いか専門家に相談するようにしましょう。
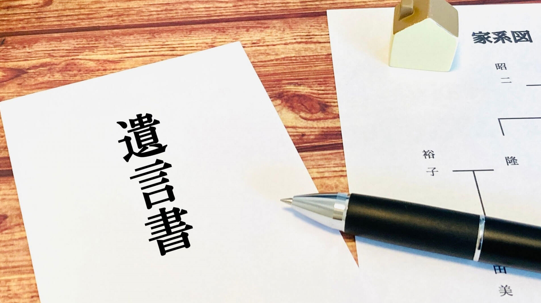
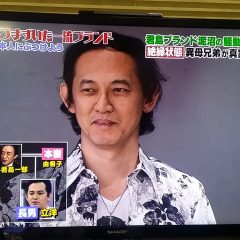
2015.12.14

2025.12.4

2020.1.4
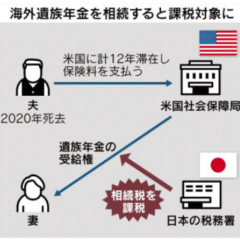
2025.5.17
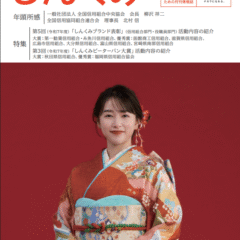
2026.1.19

2025.10.1
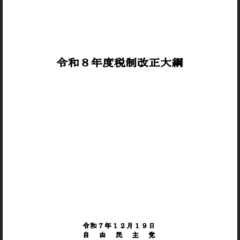
2025.12.22

2022.5.16

2026.1.21

2024.10.16
© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE