投稿日:2025年10月1日
青色申告している個人事業主の方は、妻等の親族へ青色事業専従者給与を支払っている人も多いと思います。
その支給額は、給与をもらった妻等に税金がかからないよう、いわゆる「103万円の壁」を意識し、年間103万円以内にしているケースが多いのではないでしょうか。(所得税の基礎控除額48万円+給与所得控除の最低保障額55万円=103万円)
令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除額が58万円に増額され、更に所得が低い人は最大37万円の加算があり、給与所得控除の最低保障も65万円に増額されたことから、給与の額が年間160万円までであれば所得税がかからなくなりました。(所得税の基礎控除額58万円+所得税の基礎控除額加算額37万円+給与所得控除の最低保障額65万円=160万円)
つまり、「103万円の壁」が「160万円の壁」に変わったわけです。
そのため、今年から青色事業専従者給与の額を160万円に増額しようと考える人もいると思いますが、そこに注意が必要です。
青色事業専従者給与が経費として認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
①青色事業専従者(生計を一ににする配偶者その他の親族であること等)に支払われた給与であること
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
③「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
ここで問題となるのは④「労務の対価として相当であると認められる金額であること」です。
今まで103万円だった労務の対価が、いきなり160万円に増えた理由は何ですか?
業務量が大きく増えたのでしょうか?
「税制改正があったから」では説明になりません。
青色専従者給与の額は、労務の対価として適正であるか否かが問われますので、物価の上昇や業務量の増加等による適正な見直しであれば問題ありませんが、単に「妻に税金がかならない範囲で支給している」という理由では認められません。
過大とみなされた部分は必要経費と認められませんので注意して下さい。
尚、本件は所得税の話しであり、住民税は別ですので、妻が160万円もらったら妻にそれなりの住民税がかかります。
また、青色事業専従者給与を支払った夫には配偶者控除等の適用がありませんので、併せて覚えておきましょう。

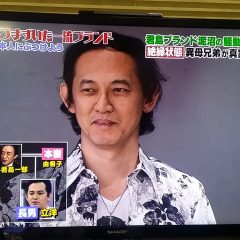
2015.12.14
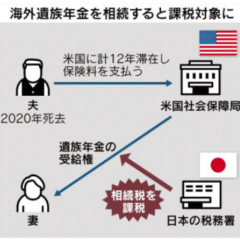
2025.5.17
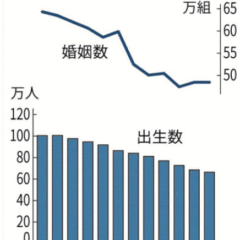
2025.12.31

2022.5.16

2025.10.1
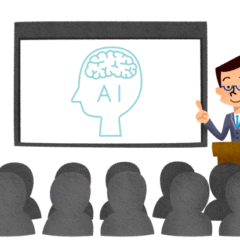
2026.1.9

2025.12.4
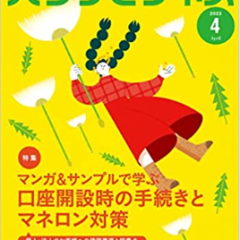
2023.3.22
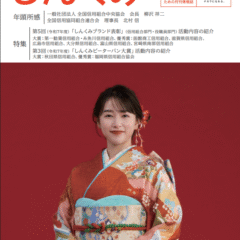
2026.1.19

2015.5.26
© 2014-2026 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE