投稿日:2018年1月11日
平成30年1月11日(木)の新聞に『成年後見人の監督怠る 国に責任 賠償命令』の記事がありました。
後見人だった継母が20年に渡って被後見人のお金を着服したことについて、国は「家事審判官が被後見人の事務が適切に行われているかどうかの監督を怠った」として、被後見人の相続人である兄へ1,300万円支払うよう命じたそうです。
後見人が私的に被後見人のお金を着服するのは、「またか…」と言った感じ。
後見人が専門職(弁護士等)以外の場合、最近は後見監督人が選任されるケースが多いのでこのようなことは少ないのでしょうが、専門職であっても着服する事件は跡を絶たないし、世の中にワルがいなくならない限りイタチゴッゴですね。
これ、信託でも同じですからね。
後見だからこんなことが起こる訳じゃないです。
「後見より信託の方がより安全、強固に財産が守られる」と言っている人もいますが、ワルは、自らの目的を達するために、どんなことをしてでも抜け道を探し出します。
自分の利益のためには相当な知恵が働きます。
信託であっても、上手いこと言って受託者に就任し、ある程度自由な裁量権を付与されれば後は自分の思い通り、後見以上に勝手に何でも出来てしまいます。
悪いことをしようと企む人の本心を見抜くのは至難の業です。
ワルは、表面上良い人が多いですし、外面良いですし、口上手いですし、親切、丁寧、優しい眼差しetc。
「騙す人が悪いのは当たり前、騙される人にも落ち度がある」と言ってしまえば簡単ですが、実際本気度MAXのワルを見抜くのは相当難しいですよ。
(僕でも未だに騙され、ややこしい話になってますから)
やはり、セカンドオピニオン、特にどことも利害関係のない中立の人複数に相談してからの方が良いでしょうね。
それでも、将来善人が裏の顔を出してこないとは限らないので、絶対ではありませんが…。
そう考えると、「自分の身を守れるのは自分だけ」と頑張っても、老後はある程度割り切りが必要なんでしょうね。
平成12年にスタートした成年後見制度は、後見人の着服等が繰り返される事件の多発を受け、制度創設から10年経った辺りから後見監督人が目を光らせるよう運用が見直されました。
信託法が施行されたのは平成19年。
今年は平成30年。
信託はスタートダッシュが遅く、盛り上がりを見せ始めたのはここ数年ですので、単純比較は馴染みませんが、嫌な予感がします。

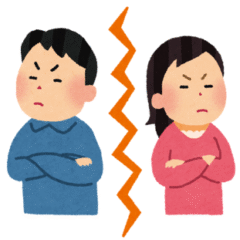
2025.7.2
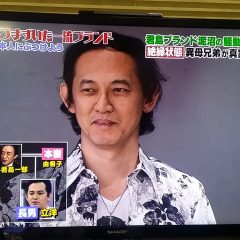
2015.12.14

2022.5.16
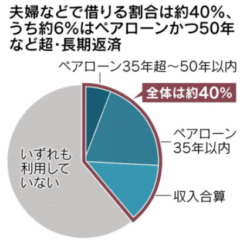
2025.7.11
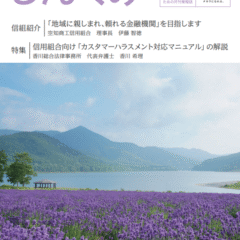
2025.7.14

2025.7.2

2025.6.20

2023.1.16
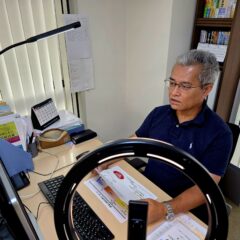
2025.7.9
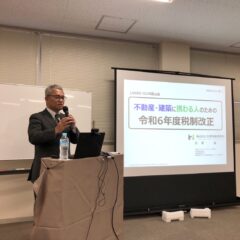
2024.2.23
© 2014-2025 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE