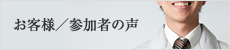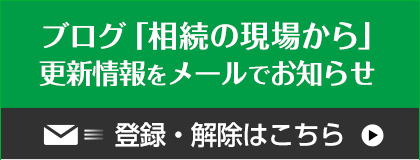-
毎年110万円ずつ孫名義で預金しています。孫はまだ小学生ですので通帳も印鑑も私が保管しています。私と孫の印鑑は別々です。
矢印アイコン
1、
-
孫の親権者は両親であり、祖父母は親権者じゃありません。祖父母が孫名義の通帳と印鑑を保管していると、名義預金とみなされる可能性があります。
-
子に贈与している事実を言うと、贈与したお金を勝手に使用してしまうかもしれないので、子には黙っておきたいのですが。
矢印アイコン
2、
-
気持ちは分かりますが、贈与は民法上の契約行為であり、贈与者の「あげる」と、受贈者の「もらう」が整っていないと、贈与は成立しません。子に黙って贈与は出来ません。
-
娘に贈与したお金で設定した定期預金が満期を迎えたので、私が継続手続きを行いました。
矢印アイコン
3、
-
娘の定期預金ですから、継続するのか・しないのかを含め、娘が手続きするのが筋です。
-
父から毎年現金を贈与してもらっていますが、父から「俺が死ぬまで絶対に使うなよ」と厳しく言われているため、その教えを忠実に守っています。
矢印アイコン
4、
-
息子の自由な使用収益権が確保されていないため、父の支配権が及んでいるとみなされ、贈与が否認される可能性があります。
-
息子の贈与税を父である私が支払いました。
矢印アイコン
5、
-
本来、贈与税は受贈者(息子)が負担すべき税金です。父が負担したのであれば、父から息子へ贈与税相当額の贈与があったとみなされますので、その分贈与金額が増えることになります。
-
贈与の度に名義を書き換えるのが面倒なので、10年分まとめて書き換えても構いませんか?
矢印アイコン
6、
-
10年分書き換えを行った年にまとめて贈与があったものとして取り扱われます。贈与した場合、都度贈与財産を移転させ、その事実を明確に残しましょう。
-
孫が今年大学に合格したので、入学金を支払ってあげようと考えています。これも贈与税の対象になるのでしょうか?
矢印アイコン
7、
-
扶養義務者相互間(配偶者・直系血族・兄弟姉妹・生計一の三親等内親族)における教育費は贈与税の課税対象外になります。
-
入学祝いや出産祝いも贈与税の対象になりますか?
矢印アイコン
8、
-
個人から受け取る入学祝い・出産祝い・結婚祝い・新築祝い・お中元・お歳暮・お年玉・お香典・お見舞い等で社会通念上相当と認められるものに贈与税は課税されません。
-
10年前に娘名義に書き換えた定期預金があるのですが、これは既に時効で娘に所有権があると考えて良いでしょうか?
矢印アイコン
9、
-
贈与ではありませんので、時効は関係ありません(開始しません)。いわゆる名義預金に該当します。
-
昔友人名義を借りて会社を設立しました。
矢印アイコン
10、
-
株主名簿に記載されている友人は単なる名義借りですので、名義株となります。
-
「相続発生前3年以内の贈与は遺産に持ち戻されて相続税を計算する」と聞きましたが、孫に贈与した現金も持ち戻されるのでしょうか?
矢印アイコン
11、
-
孫は相続人ではありませんので、普通は持ち戻されません。しかし、もし孫が何らかの遺産を相続したのであれば、孫がもらっていた相続発生前3年以内の贈与は持ち戻しの対象になります。
-
母は毎年孫へ現金を110万円ずつ贈与していました。先日母が死亡したのですが、孫が相続税を負担することはあるのでしょうか?
矢印アイコン
12、
-
孫は相続人ではありませんので、普通は相続税を負担することはありません。しかし、例えば母の加入していた生命保険の死亡保険金受取人が孫だった等、孫が何らかの遺産を相続したのであれば、孫が相続税を負担する場合もあります。
-
婚姻して20年経つので自宅を妻に贈与したいと考えています。2,000万円までだったら贈与税はかかりませんよね?
矢印アイコン
13、
-
贈与税の配偶者贈与2,000万円と暦年贈110万円を合算し合計2,110万円までだったら贈与税はかかりません。但し、贈与税の申告が必要なこと、贈与してもらった妻は不動産取得税や登録免許税、登記費用等を負担しなければいけないことに注意して下さい。
-
生前贈与のメリット(長所)を教えて下さい。
矢印アイコン
14、
-
贈与者の意思を明確に示せる/贈与財産の価値上昇分は受贈者の利益になる/世代飛ばしが可能/相続人以外の人にも贈与出来る/複数年に渡り贈与出来る/相続財産を減らすことが出来る/実行するかしないかを都度考えられる/相続税と異なり2割加算がない/将来の税制改正の影響を受けない
-
生前贈与のデメリット(短所)を教えて下さい
矢印アイコン
15、
-
相続発生前3年以内の持ち戻しがある/特別受益として遺留分の対象になる可能性がある/贈与財産の価値が下落すると残念/受贈者が先に死亡すると計画が狂ってしまう/一度に多額の財産を贈与すると税負担が重くなる/管理や形式がずさんだと名義預金とみなされてしまう恐れがある/一度あげたものは返してもらえない
-
相続税対策として生前贈与行う場合、何を比較したら良いでしょうか?
矢印アイコン
16、
-
実効税率(実質的な税負担率)を比較して下さい。
-
会社にも贈与できますか?
矢印アイコン
17、
-
出来ません。贈与者である個人はみなし譲渡所得、受贈者である法人は受贈益課税(法人税)となります。
-
会社から贈与を受けられますか?
矢印アイコン
18、
-
受けられません。贈与者である法人は時価で譲渡したとして法人税が、受贈者である個人は所得税が、それぞれ課税されます。
-
遺言だと受贈者に拒否されたり、執行上の問題が生じたりする恐れがありますので、死亡後に遺言よりも確実に財産を渡せる方法はないでしょうか?
矢印アイコン
19、
-
死因贈与契約を締結する方法があります。不動産であれば仮登記を付しておけば、更に安心です。
-
教育資金の一括贈与の問題点を教えて下さい。
矢印アイコン
20、
-
受贈者が40歳になった時に贈与しきれなかった金額がある場合等、一定の要件の下、残額に対し贈与税が課税されます。
-
贈与が成立しているかどうかを判断する基準は何でしょうか?
矢印アイコン
21、
-
①資金原資、②管理支配者基準、③自由な使用収益権の確保です。
-
相続対策として生前贈与は有益ですよね?
矢印アイコン
22、
-
その通りです。しかし、長生きリスクに備えるべく、自身の老後の生活設計をきちんと考えた上で贈与するよう心掛けて下さい。
-
相続時精算課税制度を活用し、父から評価額25百万円相当のマンションをもらいました。父が死亡した場合、どうなりますか?
矢印アイコン
23、
-
父死亡時のマンション評価が10百万円に下がっていたとしても、贈与当時の評価額25百万円を遺産に持ち戻し相続税を計算します。
-
相続時精算課税制度を活用し、母から現金3百万円をもらいました。来年は110万円ずつ贈与してもらおうと考えています。
矢印アイコン
24、
-
一度相続時精算課税制度を選択してしまうと、同じ人から暦年課税制度の贈与を受けることが出来なくなります。つまり、110万円も相続時精算課税制度の枠内で贈与を受けることになります。
-
「毎年同じ人へ同じ金額を贈与すると連年贈与になる」と聞きましたが、本当ですか?
矢印アイコン
25、
-
それが当初から約されていた贈与であればその通りです。しかし、その時その時で判断し、たまたま贈与した日が毎年近い日付だっただけであれば連年贈与になりません。